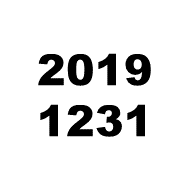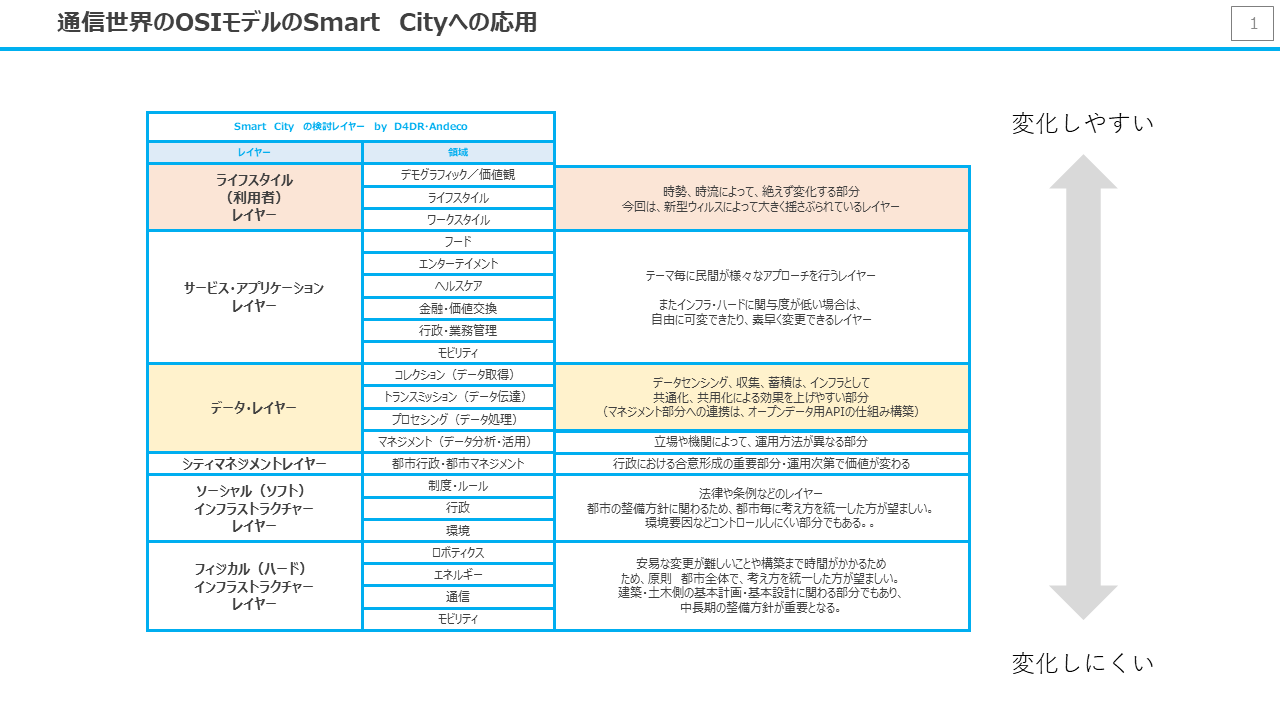移動販売のためのプラットフォームサービスをつくろう。というのが
移動販売のためのプラットフォームサービスをつくろう。というのが
アンデコという会社を創業した目的です。
小商いという言葉は昔から使われてきたのかどうかはわかりませんが、
最近、私が注目している言葉です。
みんな、オシャレ、質がよくて、さらに安くてリーズナブルなものを追い求めています。
そこに、サービスを提供する企業と資本主義が組み合わさって、大量生産、大量消費、さらにチェーンストアの拡大をしてきましたし、現在もそれは続いています。
ただ、人は、わがままなので、あまりに世の中にありふれると、つまんなさを感じて、自分しか持っていないものだったり、希少なものを追い求めたり、オリジナルにカスタマイズしたりします。
便利でイケてるからみんあiphone 使ってますが、カバーは人それぞれ好みのものを使っていたりするのも、そのアラワレだと思います。
そこで、移動販売に注目しているのは、飲食や小売りとなると、不動産の初期費用の問題があったり、人がいる場所でうまく出店できるかどうかが鍵だったりします。店舗が固定されているのが、当たり前といえば当たり前ですが、そこをうまく変革していければ、新たな可能性があると思うのが、移動販売の世界です。
とはいえ移動販売の課題として、飲食だと食材のストックとか、食べるスペースとか、エネルギー供給(ガス、水道、電気)とか、保険所の飲食業許可の課題とか、家賃払って商売している側からの反発だとか、お客さんにリピートしてもらう方法など、種々の課題だらけです。
そういった課題を一つ一つ紐解きながら、サービスづくりをしてプラットフォーム化しようというのが、めざす世界です。
東京で働いていたときに入っていたビルが、港区のでっかいビルで、地下フロアに飲食店が入っていたのですが、入っている飲食テナントは、基本はチェーンストア系でした。どうしても、毎日いっていると飽きてくるのですが、テナントは入れ替えなんてそう簡単にはできないし、メニューもチェーンストアの限界がありました。
そういった点からも、個人系や小規模系のテナントを入れてほしいなと思いつつも、現実的な話、不動産事業者からすると、都心の地価を踏まえた上での家賃設定で、払える資金力と、継続的に運営してくれる事業体ということで、チェーンストアに入居してもらうしかないんだろうというところです。
そこらへんの不動産を前提とした価値の資本主義の限界を移動販売の仕組みで超えられたら、今風でいうとシェアリング型モデルをつくろうよというのが、昨今の活動です。
地方は地方で、逆の意味で移動販売型になっているようで、徳島県のとくしまるという移動スーパーが活躍しているようです。収益的にはそこまであがらないようですが、地域の生活インフラとして重要になってきているようで、オイシックスが資本いれるなど、注目されています。
何が言いたくて、書きたかったのか、よくわからなくなってきましたが、とにかく小商い、移動販売という世界と、ICTのテクノロジー、インフラサービスを組合せて、普及するときっと面白い事、20世紀型の資本主義の限界を超える世界がつくれるだろうという事を伝えたく、そのためにいま色々と仕掛けて動いています。
20世紀型の資本主義の社会の限界を乗り越えるために、株式会社をつくって資本を集めるという資本主義のアプローチをとっているので、非常に矛盾しておりますが、もう少ししたら、色々と具体的に見えてくると思いますので、どうぞ今後とも御贔屓に、よろしくお願いします。